
近年、立て続けにお葬式があったり、異常気象で熱帯夜が続いたりして。
今年、2、3年ぶりに雛人形を出したら、みんなの顔がどえらいことに。
白いお顔が、黄ばんで、ぶつぶつができてシミだらけになっていました。
雛人形をえらく大切にしていた祖母が、おととしの12月に亡くなったのですが。お雛様たち、それがわかっているのか、悲壮感漂うお顔の表情になっていて。顔を覗き込んでみたら、目が死んでいる。
こんな悲壮感漂う状態で、いつまでも家に閉じ込めておくのも、しんどいだけだと思って。とうとう人形供養に出す時が来たのかと思ったのですが。
祖母の愛の念がこもっていることを、今更ながら実感して。手放すのも執着が出てきました。
なんともやるせなくて、お顔のシミ取りに挑戦することにしました。
雛人形の顔のシミの原因は?
ちょうど、古い段ボールから桐箱にお引越しをして、仕舞ったタイミングに起きたことだったので。もしかして桐箱に保存したことで、こんなことになってしまったの?と後悔の念が。
桐箱に入り切れなかったお内裏様とお雛様は、段ボール保存だったのですが。お二人のお顔は、他の桐箱グループよりもお顔の状態がよかったので。やはり桐箱保存が原因だったのか。
ネットで調べてみると、雛人形のお顔のシミは、湿気によってできるカビが原因らしい。
綿棒とぬるま湯
「雛人形 顔 シミ 取り方」で検索してみたら、「水で濡らした綿棒で、雛人形のお顔のシミを取る」という方法がありました。さっそく試してみました。
一番はじめに実験台になったのは、仕丁(してい)の男たちだったのですけど。写真を撮り忘れました。
もとは色白だった仕丁の一人で試してみたら、汚れが落ちた!
でもどういうわけか、汚れが落ちない部分もあって。顔があばた顔になってしまいました。
あばた部分は、水で濡らした綿棒では取れず。激落ちくんの角部分でも試したけど落ちず。
次の手段は、酸素系漂白剤。
酸素系漂白剤を、あったかいお湯で溶かして。それを綿棒に付けて塗り広げてみたら、取れました!
使った材料はこちら↓

左上の平皿が、ぬるま湯で溶かした酸素系漂白剤。
右少し下の皿が、ポットから出したお湯。
綿棒は、あばた部分や、残ったシミ部分に使いました。
綿棒は先が細くて、寝かして使っても、広い部分を一気にやさしく塗り広げるのには向いていないので、
急遽、穂先がやわらかめのナイロン筆にも助っ人してもらいました。ナイロン筆は、酸素系漂白剤なしの、ぬるま湯専門。


まず、黄ばんでぶつぶつのお顔を、ぬるま湯で濡らしたナイロン筆で撫でてみる。その段階で、けっこう簡単に汚れが取れていきます。
しかしその後、かならず汚れが残る箇所がでてきて。あばた顔になります。
そこで今度は、酸素系漂白剤入りのぬるま湯を濡らした綿棒で、残ったシミ部分をぬぐい取っていきます。
筆も綿棒も、水を使うので、きれいになった箇所の水分は、キッチンペーパーで押さえて水分を吸い取り、できるだけ乾燥しやすい状態を保ちました。
ビフォー アフター
なかでも一番ひどかったのが、三人官女の長。
この顔見た時に、心が崩壊しました。もう終わりだと。
でも、綿棒、絵筆、お湯、酸素系漂白剤、キッチンペーパーの5セットで、きれいになることが明確になって、この長のお顔にも希望が見えてきた。
いざ施術。
ぬるま湯で濡らした絵筆で、お顔を撫でてみると、思いのほか簡単に、ぶつぶつがきれいに取れました。


三人官女の長。
既婚者だから眉毛がなくて。小さい頃から、苦手な顔だったのですが。
長も女でした。
お顔がひどいときは、悲壮感たっぷりの顔だったのに。
お顔がきれいに白くなったら、表情がぱっと明るくなったのですよ。
写真撮影も快く承諾してくれたような。お顔が和らいていて。こんな表情、はじめて見ました。

雛人形の顔のシミ取りで注意した点
雛人形の頭、桐塑と石膏
雛人形のお顔は、桐塑(とうそ)で作られたものと、石膏で作られたものがあります。
ネット検索で調べたところによると、シミが出るのは石膏で作られたものらしい。
古くからある伝統的な作り方には、桐塑が使われています。
戦後、大量生産の時代とともに、型取りで大量生産ができる石膏で頭を作るのが主流になったのだそう。
私の家にある雛人形は、1980年前後に作られたもので、当時流行の7段飾り。大量生産で作られた中の1つであると予想できます。
ネットで調べると、顔をこすりすぎるとくぼんでしまうなどの情報があったのですが、そのようなことはありませんでした。石膏頭に吹き付けられているのは胡粉だと思うのですが。ぬるま湯で湿しても、表面が削れたりするようなことはありませんでした。
これが桐塑頭の場合は、今回のやり方とはまた違った方法を取るのかもしれません。
顔のパーツは日本画の絵の具で描かれている
日本画の絵の具は水彩絵の具なので、水に濡れると溶けてしまいます。
だから、眉やまつ毛部分は、水をつけないようにするか、綿棒で極軽く、ポンポンする程度の力で、汚れを落としていきます。
マスカラをした目の女性が、ティッシュで涙をぽんぽん押さえるかんじ。
唇の紅も水彩絵の具なので、触れると赤い顔料が溶け出してしまうから、触ってはいけません。
雛人形の顔は手で触らない
雛人形の顔にシミやカビができるのは、人間の手で触ったことが原因だという。
手の油が人形のお顔につくと、黄ばんでシミになってしまうらしい。
湿度が低い、乾燥した日に出し入れする
カビが発生する原因は湿度。だから雛人形は乾燥した環境に置くことが大切。
雨の日や曇り空の湿気の多い日は避け、乾燥して晴れた日に出し入れすること。
まとめ
今回、うちの雛人形の顔のシミは、ぬるま湯などで落とすことができました。これは、お顔の表面に汚れが広がっていたということ。
ネットで検索していると、内側からカビが発生して、顔の表面にぶつぶつが出てしまっているケースがあるという。
うちの雛人形も、長の顔などを見ると、そのケースかなと思ったのですが、材質が石膏で作られていたせいなのか?拭いたらきれいになる状態でラッキーでした。
3月3日を過ぎれば、また一年間、押し入れの中で保存することになります。今年の夏も長く蒸し暑い時期が続くでしょう。今年も桐箱に入れて保存するしかありませんが。雛人形用の防虫剤や、防湿剤などが必要不可欠なのだと思いました。
来年、出したとき、どういう状態になっているのか、気になるところです。

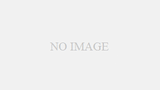

コメント